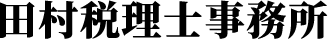医療法人を設立したら、退職金の準備も始めましょう
個人医院の場合は残念ながら退職金を設定して受け取ることはできませんが、医療法人の場合には退職金を設定すれば受け取ることができます。
では、退職金を設定することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
退職金を受け取るメリット
その一番の理由は、何と言っても「税制上の優遇=節税効果」にあります。
退職金は、その性格上、「老後の備えや老後の資金」という役割があるため、税制上の大きな優遇を受けています。
具体的には
1.退職手当等の収入金額から退職所得控除を差し引くことができる
2.さらに、退職所得の1/2にしか税金がかからない
※退職所得控除とは、退職手当の給付を受ける際に、他の所得と分けて、勤続年数に合わせた控除額を免除することをいいます。
ですから、医療法人設立と同時に、退職金規定を作成し、退職金の準備を始めれば、個人で事業を行う場合と比べ、大幅に節税することが可能となります。
退職金の適正額とは?
「退職金をなるべく多く設定すれば、それだけ多くの節税効果が期待できるのではないか?」とお考えになる方も多いと思いますが、実は退職金には「適正額」がありまして、折角退職時に多額の退職金を受け取ってもその後の税務調査で「適正額」として認められない場合、通常の所得と同様に課税されてしまう場合があるので注意が必要です。
では、退職金の適正額とは一体いくらなのでしょうか?
退職金の算定式
一般的には下記計算式に当てはめて算出することが多いです。
| 1.死亡退職金の場合 | 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率 |
|---|---|
| 2.弔慰金の場合 | 業務上の死亡の場合:最終報酬月額×36ヶ月 業務外の死亡の場合:最終報酬月額×6ヶ月 |
| 3.特別功労金 | 特別功労者には死亡退職金の30%を超えない 範囲で特別功労金を加算 |
しかしながら、実際には、「退職金を払う直前になって役員報酬が引き上げられていないか?」、「役員報酬を払った後でも医療法人できちんと利益が出ているか?」なども税務調査では見られますので、そのあたりも考慮して設定することが大切です。
退職金はいつ受け取れるのか?
退職金が設定してあれば、院長が退職をすれば受け取ることは当然可能ですが、実は「実際に退職しなくても退職金を受け取る方法」があります。それが「みなし退職」というものです。
「みなし退職」とは文字通り、実際に退職していないけれども退職したとみなすというものですが、以下の要件を満たしていれば「みなし退職」と認められると言われています。
常勤理事から非常勤理事へ職務の責任を変更した場合(代表権、経営権がある場合は除く)
理事から監査へ職務の責任を変更した場合(経営権がある場合は除く)
職務の責任を変更した後、報酬が概ね50%以上減少した場合
退職金を準備するには?
このように、退職金は院長先生がいつ頃退職(みなし退職も含む)したいのか? その時いくら欲しいのか? いくらあれば豊かな老後が送れるのか?といったライフプランから逆算することが必要です。
また、退職金は設定できても、実際に払い出す時にそれだけの原資がなければ払い出すことができませんので、どうやって資金を手当てするか?といった問題も発生します。
そこで、これから退職金を考えたい院長先生は、早めに退職金の準備をされることをお薦めします。田村税理士事務所は医療法人の退職金についての豊富な知見がございますので、まずはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ
当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。