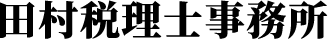新しく、会社を設立することの意義
会社をつくりたいと思う方は、景気のよしあしに関係なく以前からこの日本には多いものです。
中小企業が経済の大部分を支えているといっても過言ではないのがこの日本という国の真実ですから、会社をつくろうとする意欲にあふれた優秀な人材が絶えないことは喜ばしいことでしょう。
会社を設立したいと思ったとき、「どうやったらいいのかわからない」という方のためにこの場で手続きの流れの概略をお教えします。
会社設立時に決めること
会社設立では、さまざまな項目を決めてそれを書類に記入して提出しないといけません。
- 発起人
- 商号(社名のことです)
- 事業目的
- 所在地
ここまでは、あまり時間をかけずに決められるかもしれませんが、次のようなことも決めないといけません。
- 資本金額
- 事業年度および決算日
- 発行可能株式総数
- 設立時取締役
- 公告方法
早めに作成しないといけないアイテム
この段階で、印鑑も作成しておきましょう。社印がないと、書類をつくっても受理してもらえません。
社印には、会社代表印・会社銀行印・会社角印の3種類があります。会社代表印と会社銀行印は、同じでも問題ありませんが別々になっていることが多いです。
会社角印は日常的な業務で使用する社印ですから、あとからでもかまいませんが、会社代表印と会社銀行印は、最初のうちから出番があります。
定款とは
会社設立にあたっては定款も決めないといけません。定款とは、その会社を経営していくときのさまざまな規約をまとめたものです。(つまり、よく考えて決めておかないといけません)
定款に盛り込む内容ですが、大きく分けて3種類の事項があります。
対的記載事項
これは必ず記載しなければなりません。
記載することが義務ではない事項もあるわけですが、それは以下のように分けて解釈できます。
相対的記載事項
記載しておけば規約として有効と認められます。
任意的記載事項
記載するかどうかをその会社で自由に決められます。
何を書いたらいいかわからないという場合はご連絡いただければ、随時ご提案をさせていただけます。
定款の手続き
定款をつくったら、発起人全員が記名・捺印をしないといけません。
電子定款を利用しない場合は、3部作成しなければなりません。3部とも公証役場へ持って行き、そのうち1部は公証役場に保管されます。認証済みとなった1部を登記申請用に、もう1部を会社で保管します。
公証人役場では、その定款を認証する手続きをやってくれますが、発起人全員が実印と印鑑証明を持参で顔を揃えないと手続きができません。
発起人全員で行く場合
各人が実印と印鑑証明が必要
代理人を立てる場合
1.発起人の中の1人が代理人になる場合
代理人以外の発起人全員が署名・押印した委任状が必要
2.発起人以外の代理人を立てる場合
発起人全員が署名・押印した委任状が必要
会社の資本金の入金
公証人の定款認証が終わったら、発起人が持つ金融機関の口座に資本金を振り込みます。(定款の認証後に振り込むようにしないと、その会社の資本金にはなりませんから、絶対に順序を間違えないようにご注意ください)
この際に、その資本金を証明できる書面や払い込み証明書、そして通帳のコピーも忘れずに確保しておきましょう。
登記所の手続き
登記所での手続きでは、多くの書類を持っていく必要があります。
どんな場合でも必要な書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- (認証を受けた)定款
- 払込金保管証明書
- 印鑑証明書
- 発起人決定書か発起人会議事録
- 取締役・監査役の調査書
書類に不備がなければ設立登記申請はスムーズに受理され、この日をもって会社が設立されたことになります。
会社設立の手続きに自信がない場合
会社設立で必要な手続きを抜粋しただけでも、わりと手続きの多さや複雑さが目立ちますが、設立後にも必要な手続きはあります。(税金や社会保険の都合上、多くの官公署に会社を設立したことを届け出ないといけません)
しかし全部を独力でやらないといけないわけではありません。当事務所で手続きの大部分を代行させていただくことも可能だからです。
「会社設立をしたいとは思っても、とにかく時間が足りそうにない」という場合もありうるでしょうし、「自分たちの会社だったら、どんな手続きが必要になるのかよくわからない」という場合もありうるでしょう。
当事務所ではさまざまな会社設立のお手伝いをすでにさせていただいておりますから、あらゆるパターンについて、最適な形でアドバイスを、そして実際の手続きの代行をさせていただくことができます。これから会社をつくりたいとお考えの方はぜひご相談ください。
お問い合わせ
当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。