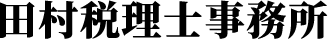会社設立をすると実践できる、数々の節税方法
会社を設立したら、「何かと資金のことを気にかけながら行動をすることが多くなる」とよくいわれています。
それは事実ですが、資金を外から探してくるだけではなく、内部で無駄を省こうと、努力するようにもなります。
実は会社を設立すると、税金を減らす方法が何種類もあります。これらの方法を適宜使いこなせば、ずいぶんと得をするチャンスがあるのです。
個人で事業をやっている方も少なくない世の中ですが、いっそのこと法人化してしまうほうが節税は楽になるでしょう。(節税がうまくいけば、資金面でも自然とゆとりが生まれます)
税率の高さと仕組みの違い
個人事業の場合、事業所得として所得税がかけられます。税率は最大で45%に達します。それも累進課税ですから、利益を増やすことができても、同時に税金まで増える結果となります。
それに比べて法人事業の場合、法人税の税率は一定です。年間所得によって変わりますが、高くても30%です。(資本金が1億円以下のケースだと800万円以下の部分15%、それを超える部分23.2%です)
所得と課税対象を分散させられるかどうかの違い
個人事業ではあくまでも個人ベースであって、所得を分散させることはできません。自分の利益は自分ひとりのものですが、税金も自分ひとりで何とかすることになります。
しかし、会社を設立して法人に変わると、家族を役員や従業員にすることも簡単にできます。(その家族には給料を支払うことになりますが、それは「会社としての利益」を少なくすることができ、税金も安くなることを意味します)
しかも役員や従業員の給料は全額が控除の対象となります。
代表たる自分への給料も当然出すことができますから、利益を思うようにうまく上げられない時期があっても、自分の給料を損金として落とすことができます。
経費の範囲の違い
経費として認められる範囲が個人事業と法人事業とではだいぶ違います。個人事業のほうが経費扱いにならない出費が多く、課税対象も多いことになります。
法人事業で経費として認められることで有名な種類を一部あげておきます。(ここにあげていないものが経費になるかどうかをお知りになりたい場合は個別にお問い合わせいただいてもかまいません)。
家賃
家賃が経費として落ちることは大きなメリットとなります。
また、法人事業では社宅を持つこともできるため、自宅を社宅とすれば、自宅の家賃の半分を経費として計上できます。
交通費
交通機関を用いて仕事のためにどこかへ行った場合や、車の費用も認められます。
福利厚生
たとえば社会保険料も経費として認められます。
会社を設立すると、代表たる自分の社会保険料も半分までは経費として計上できます。
生命保険・損害保険の保険料の支払い
個人事業の場合は、生保・損保いずれも控除される範囲は微々たる金額です。
法人事業の場合は、金額の制限なしで経費にできます。(個人的な生命保険についても、条件によっては認めてもらえます)
生命保険・損害保険の保険金の受け取り
個人事業の場合は、損害保険金は個人の一時所得とみなされるため、課税対象になります。
法人事業の場合は、損害保険金は法人の保険金であって、所得とはみなされず、課税されないようにすることができます。
赤字の繰越控除期間の違い
確定申告をするとき、欠損金の繰越控除期間に違いがあります。
個人事業の場合は3年までしか認められないのに対して、法人の場合は平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から青色欠損金、災害損失金、連結欠損金の繰越期間が7年間から9年間に延長されることになりました。
この改正で平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されることになり、具体例として、3月決算法人の場合は、平成21年3月期以後の欠損金から繰越欠損金期間が9年になります。
この期間延長に伴い、帳簿書類も9年間保存する必要があります。
また、資本金が1億円超の法人等では欠損金の繰越控除制度における損金の額に算入できる金額が、その事業年度の控除前所得の金額の80%を限度額とするという制限がつきました。
中小法人等の繰越欠損金については、繰越欠損金控除限度額の対象には入っていない為、繰越期間が延長されただけの有利なものに改正されたということになります。
一連の節税対策を実践するには、まず会社設立から
会社設立をすると個人事業のときよりもずっと節税が楽になりますが、会社設立のやり方がわからないという方も多いでしょう。
当事務所では、会社設立の手続きについても全面なバックアップをさせていただきますし、設立後の節税のノウハウについても、継続して全面的なバックアップをさせていただきます。
会社を設立したい方、会社を設立して節税したい方、そして会社設立時~設立後にかけて発生するさまざまな手続きについて手助けがほしい方は、当事務所に気軽にお問い合わせください。全力であたらせていただきます。
お問い合わせ
当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。