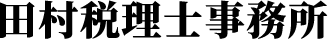Q今まで税理士さんに頼んでいなかったのですが、大体どのくらいの金額で決算・申告をしてもらえますか?
Q法人税の申告は、社長となる私でもできるものでしょうか
申告自体は可能です。
流れとしては、会計帳簿の作成 → 決算書作成 → 税務申告書作成となります。
ただ、決算書の作成までは何とかできても、税務申告書の作成というのはある程度知識がないとかなり難しいです。
また、毎年税務関連の法律が変わったりして常に最新の情報が必要となりますので、費用はかかりますが税の専門家である税理士に依頼するのが安心だと思います。
Q決算は書類を渡してどのくらいで出来ますか?
決算(申告を含む)を作成するための資料や情報が全て揃い、売上、経費、などを区分・集計されていらっしゃいましたら、通常1週間程度です。
当方に依頼するにしても、ご自身で作成されるにしても、結局は日々の記録とその集計・区分が必要となってきます。最近はパソコンソフトで簡単に集計・区分ができます。税務署のための決算ではなく、日々毎月の経営の実態を経営者ご自身が把握するために、お忙しいかもしれませんがご自身で帳簿を作成してみてください。事前にご相談いただければ、そのお手伝いをいたします。
Q法人税申告・確定申告はいつまでに申告すればいいのですか?
法人税の確定申告書の提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められており、同日までに法人税額を納付しなければなりません。
ただし、確定申告書の提出期限には例外があり、会計監査人の監査を受ける会社などは決算日から2ヶ月以内の決算が確定しないため、あらかじめ税務署長の承認を受けて提出期限を1ヶ月延長することができます。
なお、申告書の提出期限を延長した場合にも、法人税の納付期限は延長されないことに注意が必要です。
個人の方の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。また、個人の方は納税期限までに口座振替依頼書を提出することによって、振替納税を選択することもできます。振替納税を選択した場合の納付期限は4月の中旬~下旬になりますので、その年はいつが振替日になっているか確認しましょう。
Q今年になって新たに個人事業を始めました。税務署への届け出は必要ですか?
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は次のとおりです。
○所得税に関する届出書
- 個人事業の開廃業等届出書・・・事業を開始した場合
- 所得税の青色申告承認申請書・・・青色申告の承認を受ける場合
- 青色事業専従者給与に関する届出書・・・青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合
○源泉所得税に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止等届出書・・・給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(1.の「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合省略可能)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合
○消費税に関する届出書
- 消費税課税事業者選択届出書・・・免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
- 消費税課税期間特例選択届出書・・・課税期間の短縮を選択する場合
- 消費税簡易課税制度選択届出書・・・簡易課税制度を選択する場合
それぞれの届出書・申請書には提出期限等が決まっておりますので注意が必要です。
各種届出書等は各税務署に備え付けてあります。あるいは「国税庁のホームページ」からプリントアウトすることもできます。
[平成24年4月1日現在の法令等に基いて作成]
Q個人事業主です。仕事が忙しくなり妻にも手伝ってもらうことになったので、妻に給与を払いたいのですが、どうしたらようですか?
個人事業主が生計を一にしている配偶者やその他の親族に仕事を手伝ってもらった対価として給与を支払った場合、原則としてその給与は必要経費にはなりません。
しかし、次のような特別の取扱いが認められています。
○個人事業主が青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色申告者の専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
- 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。ハ、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 - 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。 - 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
○白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
白色申告者の事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
- 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。ハ、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 - 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
[平成24年4月1日現在の法令等に基いて作成]
Q個人事業主で続けるよりも会社組織(法人化)にした場合のメリット・デメリットは?
○メリット
- 事業の継続性が確保でき、知名度、信用度(特に取引先、金融機関に対して)がUPします。
- 個人事業主の場合、決算月は12月ですが、法人の場合は1月~12月まで自由に選ぶことが出来ます。
- 経営者、身内の役員、家族従業員への給料も全額経費で落とせ、営業上の所得(会社の儲け)を会社、役員、従業員に振り分けることが出来ます。
- 役員報酬は給与所得控除を受けることが出来ます。
- 経営者や役員の生命保険、損害保険を経費に出来ます。
- 社会保険料を1/2経費にすることが出来ます。
- 欠損金の繰越控除期間が法人だと7年、個人事業主の場合3年になります。
※法人の場合平成23年度の税制改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越期間が7年間から9年間に延長されることになりました。 - 退職金の適正額は経費となります。また退職金にかかる所得税も通常の所得税よりも定額となります。
退職金の所得税=(退職金-退職所得控除)÷2×税率 (分離課税となります)
H25年分以後では、特定役員(役員勤続年数5年以下)の場合、1/2税率が廃止となります。
※退職所得控除の計算の表
| 勤続年数(a) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万×勤続年数(a) 80万円に満たない場合は80万円 |
| 20年超 | 800万+70万×(a-20年) |
○デメリット
- 設立手続き、廃業手続きが必要になります。(費用がかかります)
- 役員改選登記が2年に1回必要となります。(株式譲渡制限会社の場合は10年)
- 正規の会計帳簿を作成しなければならないため、経理事務が複雑になります。
- 青色申告特別控除が使えません。
- 法人の場合、赤字でも均等割税額がかかります。
- 接待交際費に制限があります。資本金1億円以下の場合、600万円までの10%と600万円を超える部分が経費にできません。
H25年税制改正により、H25.4.1~H26.3.31に開始する事業年度では、資本金の額が1億円以下の法人に限り、支出交際費の額が800万円以下の部分については全額損金算入することができるようになりました。
Q法人税は、いくらかかるの?(ex:課税所得100万円)
法人の規模によって次のようになります。
○決算期末における資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等の場合
- 決算期が平成24年4月1日以後に開始する事業年度である場合
課税所得100万円×法人税率15%=15万円 - 決算期が平成24年4月1日前に開始した事業年度である場合
課税所得100万円×法人税率18%=18万円
(注)普通法人が決算期末において次に掲げる法人に該当する場合を除く
- 次のいずれかの法人
イ、次のいずれかの法人(以下「大法人」といいます。)との間にこれらの大法人による完全支配関係がある法人
01. 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
02. 法第4条の7に規定する受託法人(以下「受託法人」といいます。)
03. 相互会社(外国相互会社を含みます。)ロ、当該普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をいずれか一の大法人が有するものとみなしたときにその一の大法人による完全支配関係があることとなる法人 - 受託法人
- 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
- 相互会社(外国相互会社を含みます。)
○決算期末における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人及び上記(注)に該当する場合
- 決算期が平成24年4月1日以後に開始する事業年度である場合
課税所得100万円×法人税率25.5%=25.5万円 - 決算期が平成24年4月1日前に開始した事業年度である場合
課税所得100万円×法人税率30%=30万円
[平成24年4月1日現在の法令等に基いて作成]
Q医療費控除について。家族の分も対象になるのか?控除の対象にならない医療費もある?
医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に対象となります。この場合の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
医療費控除の対象とされる医療費は、個人がその年中に支払った診療等の対価のうち、通常必要と思われるもので、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
あくまで、診療・治療に対して支払う医療費なので、次にあげるものは医療費控除の対象ではありません。
- 医師等に払う謝礼金
- 人間ドッグなど健康診断の為の費用(健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を受けた場合は、医療費控除の対象になります。)
- 美容整形・エステに関する費用
- 健康維持・増進のためのサプリメント、漢方薬、疲労回復の為の栄養ドリンク
(医師の処方にて服用するものなど、治療・療養のために必要なことが明らかな場合には、医療費控除の対象になります。) - 入院した際の自己都合による差額ベッド代
- 通院のための自家用車のガソリン代や、駐車場代
この他にも控除対象になるものと、ならないものの判別が付けにくいものもたくさんありますので、迷われ場合は領収書を保管の上、ご相談ください。
Q業績が悪いので、期の途中で役員報酬を減額することはできますか?また、いつでも変更可能ですか?
役員報酬の改定は、その会社の株主総会または取締役会等で決議されればいつでも変更は可能ですが、税務上、損金(必要経費)として認められるには、条件があります。
役員報酬を損金として認める給与は、以下の3つタイプがあります。
定期同額給与 事前確定給与 利益連動給与
利益連動給与は、上場企業しか適用できないので、説明いたしません。
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
前確定給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいいます。税務署に定められた期限内に届出を提出する必要があります。
定期同額給与、事前確定給与どちらにも業績悪化事由による改定の条件が明示されています。その条件に合致する場合のみ、損金として認められます。業績が悪化したのでまずは役員から給与を引き下げる、という姿勢は大変立派なことだと思いますが、臨時に改定する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
通常の役員報酬の改定(増額・減額どちらも)につきましては、事業年度開始から3ヶ月以内に改定してください。
経費として認められなかった場合は、法人税の計算の際に認められない額を利益に加えて税金を計算し、なおかつ、給与を得た役員には得た給与に対して全額、通常どおり所得税が課税されます。
Q資産として計上しなければいけないものは?
資産に計上する金額基準には10万円以上・20万円未満・30万円未満の三基準があります。
この基準は通常一組などで判定しますが10万円以上を資産に計上するのが原則です。
しかし、20万円未満の資産の場合、一括償却資産として三年で均等に償却が可能です。
また、中小企業者等で青色申告を選択していますと30万円未満の一定の資産について300万円を限度に全額を経費にすることが出来ます。
Q会社の事業年度は自由に決められるのですか?
1年以内であれば、自由に設定することができます。例えば、半年にしても良いのですが、その場合、決算を年2回行う事になります。よって通常は、最長の1年間にする場合が多いようです。又、5月10日~翌5月9日までと月の途中で区切っても構いません。
Q一人当たり5,000円以内の飲食代は交際費にならないと聞きますが、二次会も5,000円いないであれば交際費にしなくていいのですか?
ご質問の「交際費にならない」というのは、「税法上の損金になる。」という意味で解釈してお答えします。二次会、三次会と複数にわたって行われた場合、それぞれが単独であるか一体であるかによって取扱いが変わります。単独の場合とは、例えば一次会はレストラン、二次会はラウンジ等別の業態の飲食店を利用しているときは、別々に5,000円以内かどうかを判定します。一体の場合とは、同一の飲食店で支出する金額を分割して支払っていると認められるようなときが該当し、この場合は一次会、二次会を合計した金額で5,000円以内かどうかを判定します。
Q役員の退職に伴い退職金を支給したいのですが、金額に上限はありますか?
退職金の上限は法律上は決まっていません。手続き上は、株主総会の決議で500万円でも1億円でも自由に決めることができます。しかし税務上過大な退職金は、会社の経費として認めてもらえません。不相当に高額な部分の金額は、従事した期間、退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職金の支払状況等に照らしその退職役員に対する退職金として相当であると認められる金額を超える部分の金額とされおり、実に抽象的な判断基準となっています。
実務では一般的に次の算式を使って退職金を算定している場合、過大退職金とされるリスクはほとんどないと思われます。
役員退職金額=退任時の最終月額報酬×在任年数×功績倍率
算式のうち功績倍率は、代表取締役で3倍、それ以外の取締役で2倍程度がよく使われています。
Q資本金100万円で法人を作ろうと思っています。届出る書類はどのようなものがありますか?
- 法人設立時
法務局(法人設立登記申請) - 法人設立後
税務署・都道府県税事務所・市町村への届出(税金関係)
年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)
労働基準監督署・ハローワークへの届出 (労働保険・雇用保険)
Q交際費はいくら使っても経費になるのですか?(法人)
法人が支出した交際費は、会計上(決算書や損益計算書)は経費となりますが、法人税の計算上は原則として損金になりません。
ただし、期末の資本金の額が1億円以下の法人は、交際費の額から下の②の損金不算入額を差し引いた金額を法人税計算上も経費として取り扱います。
- 期末資本金の額が1億円超の法人
支出交際費の全額が損金不算入 - 期末の資本金の額が1億円以下の法人
イ、支出交際費の額が600万円以下
支出交際費の額×10%=損金不算入額ロ、支出交際費の額が600万円超
支出交際費の額-600万円)+(600万円×10%)=損金不算入額
H25年税制改正により、資本金の額が1億円以下の法人では、支出交際費の額が800万円まで全額を損金算入することができるようになりました。800万円を超える部分については損金不算入になります。
なお、この制度はH25年4月1日~H26年3月31日に開始する事業年度で適用されます。
Q青色申告にするには具体的にどのようにすればいいでしょうか?(個人)
(1)青色申告の申請手続
それぞれの区分に応じた提出期限までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
(2)青色申告者の帳簿書類とその保存
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。
お問い合わせ
当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方、悩んでいる方は一度ご相談いただくことをお勧めします。
初回から専門家が本気でお聴きしますので、どうそご安心してご相談ください。